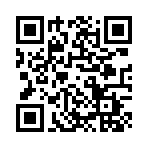いけばな教室 ~生徒さんの作品集12/27~
今年最後のレッスンです

●今日のテーマ
・基本立真型・投入
・基本傾真型・盛花
・第一応用立真型・投入
・第一応用傾真型・投入
・第一応用立傾真型・盛花
・第二応用立真型・盛花
・第五応用立傾真型・盛花
●今日の花材
・若松
・葉ボタン
・ピンポンマム(黄・緑)
・チューリップ(赤)
●追加アイテム
・水引(紅白・金銀)
お正月花です。
オーソドックスなお正月花に、春の兆しを表すチューリップを選んでみました

お正月花には、それぞれが持つ由来や意味があります。
松・竹・梅・千両・葉ボタン・柳… それぞれのお話もお伝えしながら、生けていただきました。
生けた後は、水引でデコレーション
調べてみると、水引の結び方にもいろいろあるのです。
・一度きりで終わることを願う結び方⇒結びきり、淡路結び…
・何度も訪れることを願う結び方⇒蝶結び…
簡単そうに見えて、結ぶのが意外と難しいのです。
みなさん苦心してとてもキレイに結びあげました。
どれも日保ちのする花材をご用意しました。
お家に帰ったら、これに思い思いの花材を加えて、ご自分らしいお正月花を完成させてくださいね

今年のいけばな教室は、これで最終になります。
生徒さん、日和カフェのみなさんはじめ、今年一年どうもありがとうございました。
新年は、少し遅めで1月31日(木)スタートとなります。
また元気な顔でみなさんとお会いできればと思います。
どうぞ、よいお年をお迎えください。
2007年12月29日 Posted by 主宰:一色はな at 16:08 │Comments(0) │生徒さんの作品集
お花のはなし vol.12ポインセチア

レッスンで使用したお花についてコラムを書いています

07'10月までの「お花のはなし」はこちら ⇒http://blog.livedoor.jp/issikihana/archives/cat_50030570.html
種 類:トウダイグサ科ユーフォルビア属
原産地:メキシコ西部
花言葉:私の心は燃えている
誕生花:12月5日 9日 22日
Merry christmas!!
クリスマスの花といえば、ポインセチア。
シーズンになると、至る所で見かけますね。
お花を習っていれば、興味が沸かないはずがないと、
レッスンでは用いていませんが、今回はクリスマスシンボル
 ポインセチアについて取り上げます。
ポインセチアについて取り上げます。ポインセチアの歴史は、メキシコのインディアンに遡ります

原住民インディアンは、ポインセチアから赤い色素を採取し、また茎から出る白い液は解熱剤にするなどして、自生していたポインセチアを生活に役立てていました。
ポインセチアは薬草だったのです。
その後、赤はキリストの血の色、緑は農産物の成長を表しているとして僧から珍重されるようになります。
ポインセチアが広く知れ渡るようになったのは、メキシコ駐在のアメリカ大使ポインセット氏に所以。
ポインセット氏は植物学者でもあったため、発見したポインセチアの情報をアメリカの園芸業界などへ広めました。それをきっかけにポインセチアが流通されるようになりました。
ポインセチアの名前は、このポインセット使に由来しています。
原産国とされるメキシコ合衆国では、「ノーチェ・ブエナ(聖夜)」と呼ばれています。
日本では、大酒飲みの人の赤い顔がポインセチアの赤色に似ていることから、"猩々木"(しょうじょうぼく)と別名もあります。
聖なるポインセチアですが、花持ちが悪く茎が短いため、切花ではほとんど流通しません

いけばなで使用するときも、特殊な処理が必要になります。
鉢物で楽しむのがよいお花です

花言葉もステキですね

クリスマスプレゼントに限らず、溢れる愛情を伝える有効なツールになるでしょう

2007年12月25日 Posted by 主宰:一色はな at 22:23 │Comments(0) │お花のはなし
2007'ラストレッスン@家元教室
在籍している家元教室、20日が今年最後のレッスンでした。
講師は茜家元。
親しみやすく気さくなお人柄で、大好きなお方です。
家元就任当初、私もどんな方なのだろうとドキドキしていたのですが、レッスンを受けてみて
「この方になら着いていっていいな 」と確信した事を覚えています。
」と確信した事を覚えています。
テーマは「クリスマス花」と「正月花」。
茜家元のデモ作品。年末なので出血大サービス
一部ですがご紹介。
ものの2.3分で生けちゃうのですよ。 圧巻


(クリスマス花。ポインセチア、ユーカリ、カスミソウ)

(正月花。黒松、大王マツ、イイギリ、椿)
「自由と個性を重視するのが、草月の魅力」
「素材と対話すること」
「日常生活に密着した現代いけばなの代表」
「花は生ければ人になる」
この日も家元は言われていました。
人はもちろん、素材にも個性があります。素材に対して、無理矢理な操作は出来るだけしません。
例えばそこに曲がった枝があったなら、その曲がりから作品を発展させようと思うのが草月です。
「欲望ありきでなく、個性と素材を尊重したうえで作品が成り立つ」とでもいいましょうか。
こういった考えが、私には合っているなあと思っています。
雲の上のようなすごい方に関わらず、汗をかきながら生徒さんお一人お一人に誠実に丁寧に真摯に講評する家元を拝見して、私の中の、不安や戸惑いが自信に変わり 自信が確信に変わりました
自信が確信に変わりました
私も愛する生徒さんのため、2008年もがんばるぞ
講師は茜家元。
親しみやすく気さくなお人柄で、大好きなお方です。
家元就任当初、私もどんな方なのだろうとドキドキしていたのですが、レッスンを受けてみて
「この方になら着いていっていいな
 」と確信した事を覚えています。
」と確信した事を覚えています。テーマは「クリスマス花」と「正月花」。
茜家元のデモ作品。年末なので出血大サービス
一部ですがご紹介。
ものの2.3分で生けちゃうのですよ。 圧巻



(クリスマス花。ポインセチア、ユーカリ、カスミソウ)

(正月花。黒松、大王マツ、イイギリ、椿)
「自由と個性を重視するのが、草月の魅力」
「素材と対話すること」
「日常生活に密着した現代いけばなの代表」
「花は生ければ人になる」
この日も家元は言われていました。
人はもちろん、素材にも個性があります。素材に対して、無理矢理な操作は出来るだけしません。
例えばそこに曲がった枝があったなら、その曲がりから作品を発展させようと思うのが草月です。
「欲望ありきでなく、個性と素材を尊重したうえで作品が成り立つ」とでもいいましょうか。
こういった考えが、私には合っているなあと思っています。
雲の上のようなすごい方に関わらず、汗をかきながら生徒さんお一人お一人に誠実に丁寧に真摯に講評する家元を拝見して、私の中の、不安や戸惑いが自信に変わり
 自信が確信に変わりました
自信が確信に変わりました
私も愛する生徒さんのため、2008年もがんばるぞ

2007年12月21日 Posted by 主宰:一色はな at 22:05 │Comments(0) │その他
「日和」ご覧ください
いけばな教室 ~生徒さんの作品集12/13~
毎月第2木曜日の方のレッスン。
今日の花型
・デッサン+自由花
・第一応用傾真型・盛花
・基本傾真型・盛花(逆勝手)
・自由花+平面分割①
・第五応用立真型・盛花
今日の花材
・晒しミツマタ
・バラ(赤)
・クッカバラ
・サンゴミズキ(黄)
・デンファレ(白)
白⇒晒しミツマタ
赤⇒バラ
緑⇒クッカバラ
と、今日はクリスマスカラーの花材にしました

またクリスマス用のオーナメントも用意。
出来上がった作品にデコしていただきました。
いつもの花型に少し加えるだけで、パッとクリスマスな雰囲気になります。
皆さん楽しんで、飾ってました

いけばなでも十分にクリスマスを演出できます

お家でも飾って楽しいクリスマスを過ごしてくださいね。
今日の教室はクリスマスカラー一色

ところどころにクリスマスを演出してみました。
雰囲気を高めるべく、密かに私もクリスマスチックないでたちで。
いつも日和カフェへ飾るお花も、今日はクリスマスツリーをイメージしていけてみました

2007年12月14日 Posted by 主宰:一色はな at 21:42 │Comments(0) │生徒さんの作品集
お花のはなし vol.11アカメヤナギ
レッスンで使用したお花についてコラムを書いています
07'10月までの「お花のはなし」はこちら ⇒http://blog.livedoor.jp/issikihana/archives/cat_50030570.html

種 類:ヤナギ科ヤナギ属
花言葉:強い忍耐
誕生花:12月7日 12月7日
枝ものになりますが、この時期のレッスンでよく使う花材です。
調べてみると面白いエピソード
お花のはなしでご紹介することにしました
名前のとおり、ヤナギの仲間になります。
アカメとは、秋口になると花の包が赤く霜焼けすることから「赤芽柳」名付けられました。
この赤は、霜焼けだったとは
子供の耳たぶのようでカワイイですね
やがて、この包が破けて雄花が出てきます。
銀色でフワフワとしたビロード状の毛並みのよい雄花です。
雄花の状態になると「銀芽柳」とも言われるようになります。

生ける際のマメチシキ的なこととしては
枝全体を見ると、枝の表裏がわかりやすい枝です。
赤い方が陽表(ひおもて)
陽表=地中に植わっていたとき太陽が当たっていた向き。
緑色のほうが裏になります。
生けるときは、赤いほうが正面にくるようにして生けましょう
また、枝が柔らかく撓め(ため)がかなり効きます。
撓め(ため)=枝を曲げて表情を変えたり、作品全体の味を出すこと。
撓めてできた曲線の面白さを生かして、生けるとよいでしょう。
扱いやすい枝なので、お稽古花として人気のある花材です。
ビックリしたのは、パリでブーケレッスンを受けたとき もネコメヤナギを使用したこと
もネコメヤナギを使用したこと
思いのほかベストマッチ
シック&ポップな仕上がりになりましたよ。
日本に限らず、和にも洋にも人気の花材です。

07'10月までの「お花のはなし」はこちら ⇒http://blog.livedoor.jp/issikihana/archives/cat_50030570.html

種 類:ヤナギ科ヤナギ属
花言葉:強い忍耐
誕生花:12月7日 12月7日
枝ものになりますが、この時期のレッスンでよく使う花材です。
調べてみると面白いエピソード

お花のはなしでご紹介することにしました

名前のとおり、ヤナギの仲間になります。
アカメとは、秋口になると花の包が赤く霜焼けすることから「赤芽柳」名付けられました。
この赤は、霜焼けだったとは

子供の耳たぶのようでカワイイですね

やがて、この包が破けて雄花が出てきます。
銀色でフワフワとしたビロード状の毛並みのよい雄花です。
雄花の状態になると「銀芽柳」とも言われるようになります。

生ける際のマメチシキ的なこととしては
枝全体を見ると、枝の表裏がわかりやすい枝です。
赤い方が陽表(ひおもて)
陽表=地中に植わっていたとき太陽が当たっていた向き。
緑色のほうが裏になります。
生けるときは、赤いほうが正面にくるようにして生けましょう

また、枝が柔らかく撓め(ため)がかなり効きます。
撓め(ため)=枝を曲げて表情を変えたり、作品全体の味を出すこと。
撓めてできた曲線の面白さを生かして、生けるとよいでしょう。
扱いやすい枝なので、お稽古花として人気のある花材です。
ビックリしたのは、パリでブーケレッスンを受けたとき
 もネコメヤナギを使用したこと
もネコメヤナギを使用したこと思いのほかベストマッチ

シック&ポップな仕上がりになりましたよ。
日本に限らず、和にも洋にも人気の花材です。